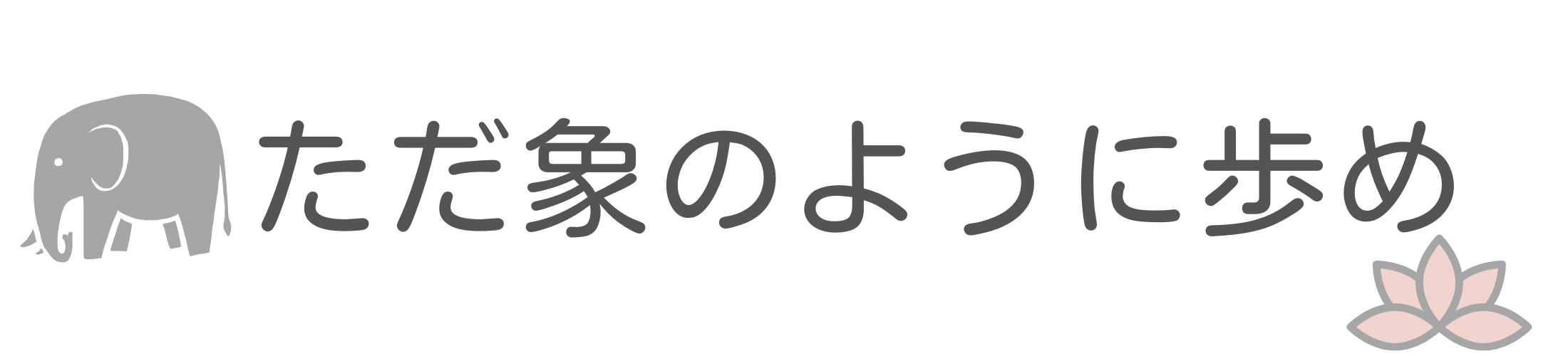本の話がしたい!ということで、火の鳥シリーズで一番好きな鳳凰編について。

生後すぐの事故により片目片腕を失った我王。周囲に嫌われ蔑まれ続けた我王は、憎悪にまみれた人生を送り極悪人になり果ててしまった。己の欲望のままに他人を踏みにじる我王の人生は、ある上人との出会いによって劇的に変化する。上人の導きによりひたすら仏を造り続ける我王。裏切りや権力争い、憎悪や嫉妬に巻き込まれながらさらなる苦難の道を歩むことになるが、ついに我王はこの世で生き抜くことを決意するに至る。
とってもオブラートに包んだあらすじなので、我王のたどる道の細部はぜひ実際に本で確認してください。私の人生の指針となる本の1つとなっています。
我王と茜丸
鳳凰編の主要人物の1人に、茜丸がいます。我王とは対照的に、優秀で将来有望な若き仏師だった茜丸。しかし我王との出会いにより、利き腕を傷つけられてしまいます。もう仏を彫ることができないと絶望する茜丸でしたが、もう片方の腕があることに気づき、仏師としての道を究めていきます。
しかし自分の実力が権力者に気に入られたあたりから、茜丸の行く先に翳りが生じます。ひたすらに仏師の道を歩んでいた姿が失われ、権力に囚われる茜丸。その執着は、死の間際まで続くことになりました。
一方の我王。若き日に嫉妬心から茜丸の腕を傷つけた因果は、のちに自分に返ってくることになります。最終的には両腕を失う我王。しかしその頃には我王は憎しみや嫉妬心、欲から解放されていました。世界の美しさに涙した我王は、両腕を失いながらも仏を造り生き続けていきます。
鳳凰編の何がいいのか?我王の悟り
悲惨な人生を歩んできた我王が、上人の導きにより「このために生まれてきた」仏を造る道を歩む。信頼していた上人にさえ裏切られた(と勘違いした)我王は、絶望のどん底に陥りながらもひたすら仏を造り続けます。
欲にまみれた現世を厭い、即身仏への道を選んだ上人。しかし我王はそんな世の中で「生き抜いて見せる」ことを決意するに至ります。
「美しい……!」
『火の鳥 鳳凰編』 手塚治虫
「おれとしたことが……」
「あの、手を斬られたときにも出なかった涙が……!」
「なぜおれは泣くのだろう」
「なぜこんなに天地は美しいのだろう」
「そうだここではなにもかも……生きているからだ!」
(中略)
「良弁さまあなたがなぜこの世から逃げてしまわれたのかわかります」
「だがおれは死にませんぞ」
「……おれは生きるだけ生きて……世の中の人間どもを生き返らせてみたい気もするのです」
私はここで我王は最終的な悟りを得たと解釈しています。我王に降りかかった数々の出来事を描写しながら、1人の人間が悟りを得る瞬間までを描き切った手塚治虫のストーリーの妙がこのラストに集約されていると思います。我王の悪行を擁護するわけでも、このために必要だったというわけでもなく、歩んできた道がすべて1つになった瞬間は圧巻です。
「乱世編」で鞍馬天狗として再登場
火の鳥ではストーリーをまたがって人物が再登場することがよくあります。我王もその1人。源平合戦をモチーフにした「乱世編」で鞍馬天狗として登場します。

私が注目するのは、乱世編の主人公弁太が初めて鞍馬天狗に会った場面です。
「おまえさま両手ともないので……?」
『火の鳥 乱世編』 手塚治虫
「ああどこかへ落としてしもうたわ」
鞍馬天狗(我王)が両腕を失った紆余曲折を語ることもなく、ただ「落とした」とするところ。生きる上での苦難をすべてこういう風に解釈して受け流せたらどれほど楽に生きられるだろうか。たったこれだけの言葉で鞍馬天狗の究極の悟りを表現してしまった手塚治虫に、やっぱり脱帽せざるを得ない。月並みだけど、本当に天才としか言いようがないです。
折に触れて読みたい本があるということ
それほど読書家ではないけれど、本から得られるものは大きいと感じます。ノウハウ本的なものも読むし役立ちますが、ファンタジーやフィクションといったジャンルからの方が、人生の指針的な考え方を学ぶことが多いような気がしています。
フィクションであっても、結局は「人」が書いたもの。そう考えると、その中には書き手の人生や考え方が詰まっているとも言えます。そのため実在しない人物や場面からでも、人の生き方のリアリティを感じられるのかもしれません。
火の鳥は大変有名な作品で私個人が解説せずとも知っている人は大勢いると思いますが、もし未読であればぜひ手に取ってみてほしいと思います。何だかわからないけど心がもやっとする、頭がクリアにならない、という時に、何か響くものがあるかもしれません。
以上で終わります。